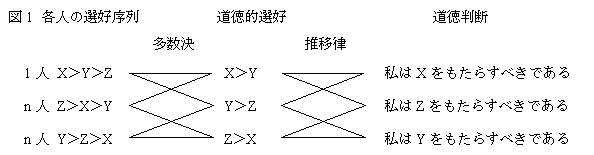
奥野 満里子
功利主義に対する代表的な批判の一つは、効用の(快苦の、あるいは最近の功利主義理論で言われるところでは、欲求・選好の強さの)個人間比較の困難さ、もしくは不可能性を指摘するものである。しかし、我々人間にそのような比較が完全に正確にできると断言する者は、実際、功利主義者の間でも滅多にいない。にもかかわらず、功利主義者は、たとえ不完全にしかできないにしても、道徳的決定にあたってはそうした個人間比較がどうしても必要だと主張するのである。では、(1)
功利主義者が、ある種の個人間比較――後に述べるように、これは選好強度の個人間比較として考えられる――の必要性を主張するのはなぜか。また、(2)
その種の比較を敢行する場合、比較を行なうためにどのような手続きが必要であるか。そして、(3)
その種の比較に困難が生じるとしたら、それは正確にはどの部分に生じるのだろうか。本稿はこれらの点について考察を試みる。
効用の個人間比較は不可能だと論じて功利主義を批判するのは簡単なことである。他人の内面的心情を正確に把握すること、ましてやそれを異なる人間の間で正確に比較することなど不可能なことは、誰しも承知している。しかし、我々が日常において、他人の幸福を慮って彼の気持ちを推し量ろうとしたり、彼の望みや欲求を推し量ろうとしたりすること、そして人々の欲求が対立する場合には双方の言い分のどちらがより切実であるかを見比べようとしたりすることも、よく見られる事実なのである。では、なぜ我々はそのような「所詮、正確にはなしえない」比較をしようとするのか。この問いを考察することは、不正確ながらもその種の比較を行おうとする普通の人々にとっては十分に価値があるだろう。そして、多くの普通の人々が日常生活において現にそうした比較を行おうとしているのなら、「比較は無理だ」とのみ指摘するより、その種の比較がどのような点において困難であるのかを詳しく検討してみることこそ必要であると言えよう。
1. 問題の確認:効用比較とはいかなる種類の比較であるか
功利主義は、「道徳的に正しい行為とは、当の行為によって影響を受ける人々全体の幸福(これは、快から苦を差し引いた剰余とされる)もしくは選好充足を最大限にもたらす行為である」とみる倫理学説である。人々の幸福や選好充足は、個々人の快苦、もしくは選好充足に還元される。そこで、功利主義では当然、個々人の快苦や選好充足の度合いを測定し、それを異なる個人の間で比較し、そうして人々全体の幸福や選好充足の総量を査定する、という作業が必要となる。
いま「快苦もしくは選好充足」と述べたように、功利主義には大まかに分けて快楽説をとるものと選好充足説をとるものがある。しかし本稿では、いずれの説をとるにしても、功利主義における効用の比較は選好の比較によっておこなわれる、と想定して論じることにする。というのも、ベンサムはさておき、快楽説をとるJ.S.ミルやシジウィックの理論においては、快楽の比較は実際には選好の比較によっておこなわれるのである(彼らはベンサムの快楽説を継承しつつ、より深い洞察を加えて議論を発展させたと私は考える。快楽説における選好概念の導入を評価した論文としてはUchii 1998を参照されたい)。そして、私が見る限り最も洗練された快楽説を展開させたシジウィックの議論においては、快楽はそれを感じる主体の欲求対象となるような感情として捉えられ、その快苦の「大きさ」は、それぞれの感情に対する欲求や嫌悪、言い換えれば選好の程度によって測定され比較されるのである。やはり快楽説価値論(本人の表現では、幸福理論)をとる現代の功利主義者R.B.ブラントも、選好強度の比較によって幸福の比較をおこなう。他方、選好充足説の代表的な主唱者であるR.M.ヘアの理論においては、もちろん、必要なのはまさしく選好の比較であるとされる。
こうして、いずれにしても、功利主義は人々の選好を比較考量して道徳判断を導くような形の理論である。つまり、なすべき行為の選択にあたって、可能な行為の選択肢とそれらがもたらす事態に関する人々の選好(1)を比較考量して決めようとする理論である(もっとも、ヘアのような理論においては、考慮される選好は理論上はすべて道徳判断を下す主体自身の選好として扱われるのだが、本論ではヘアの理論も実質的には個人間比較に等しい作業を行わねばならないものとみなして考察する。なぜなら、ヘアの理論が判断主体自身の複数の選好を比較考量する形で論じられているとはいえ、それら複数の選好とは、自他を含めた異なる人々の選好を再現したものにほかならないからである。ヘア 1995参照)。
このようなやり方をとるとき、我々は問題を抱えることになる。すなわち、人々の選好をいかにして比較し、どのように道徳判断に反映させるのかという問題である(我々はまた、未来のある時点の選好と現時点の選好とを比較する問題も抱えている。以下で私が「人々の選好」の比較の問題を語るとき、異なる時点における選好の比較という問題も同時に論じているものと理解されたい)。
もっとも、これに類する問題は、功利主義に限らず、多くの道徳理論に伴うものである。人々の選好を何らかの仕方で考慮に入れる道徳理論は、それらの選好をいかにして考慮に入れるかという問題には必ず直面する。また、たとえ快楽説も選好充足説も採用しない場合でさえ、人々の善を考慮する道徳理論である限り、各人にとっての善をいかに扱い、道徳判断に反映させるかという問題は生じるのである。
ただし、功利主義においては、選好の扱いに関してかなりはっきりとした方針が決められている。人々の選好を強さの程度に比例して重んじ、人々の選好充足を最大化するような行為が正しいと判断するのである。この場合、選好強度は測定可能であり、しかも個人間で比較可能だと仮定されている。功利主義が特に批判されるのは、この仮定に対してである(もっとも、この仮定も功利主義に限らず人々の選好の強度を比較する道徳理論全てに当てはまる。というのも、選好強度の個人間比較をおこなう道徳理論には、同じ強さの選好を単純に等しく重んじるという以外の見解もありうるからである)。すなわち、人々の選好を何らかの仕方で重んじ、それらを勘案して一つの道徳判断を下さなければならないということは認めたとしても、選好の強さを測定したり、それを個人間で比較したりするのは無理だと反論されるのである。
本論は、選好強度の個人間比較は必要か、そのような比較をするとすればいかにして行うか、そして、その比較に幾つかの困難があるとすれば、それは正確にはどのような点にあるかを明らかにする。
2. 選好強度の測定・個人間比較の可能性を否定した場合のパラドックス
その検討にあたり、私が議論の端緒としたいのは、選好強度の測定やその個人間比較の可能性を否定した場合についての考察である。この可能性を否定しながら人々の選好を何らかの仕方で考慮に入れた道徳判断を下そうとするとき、考えられる提案は、選好序列のみの考察に基づいて道徳判断を導くというものである。すなわち、我々には他人が一方より他方をどのくらい強く望むかはわからないとしても、二つの選択肢のどちらを望むか、また複数の選択肢をどの順に選好するかという選好順序は彼の選択行動やその他の言動からある程度はわかるとされる。そこで、各人の選好順序だけを考慮して道徳判断を導けるなら、選好強度の測定・比較に批判的な人々にとっては好都合である。しかし、選好強度の測定とその個人間比較の可能性を否定する場合、道徳判断を下そうとする者はしばしば逆説的な事態に直面する。以下ではこのことを、ケネス・J・アローの一般可能性定理を参考にして論じることから始めてみたい。
多数決と推移律による方法
アローの一般可能性定理とは、効用の個人間比較の可能性を排除した場合、個人的選好を集計して社会的選択を導こうとするいかなる方法も、我々が逆説的とみなすような事態を生じる可能性があることを示したものである(Arrow 1963 邦訳p. 95)。アローはこの定理を、社会的決定の文脈で、とくに個人的効用関数から社会的厚生(効用)関数を構成できるかという経済学の見地から論じている。しかし、我々は彼の議論を、個々人の選好体系(選好順序のほか、選好の強さをも含めた、様々な対象に対する主観的態度)についての考慮に基づいて個人が(私が)どのような道徳判断を下しうるか、という問題として読み替えることが可能である。このように読むとき、アローの議論は、なすべき行為について道徳判断を下すにあたって、1) 私がもたらしうる事態が三つ以上あり、2) それらに関する各人の選好順序は確定できると仮定するが、3) ある人の選好体系と別の人の選好体系を選好強度の点で比較せず、4) 主に多数決と推移律を用いて集計しようとするとき、集計の手順によって矛盾する道徳判断がいずれも正当化可能なものとして導かれてしまう――あるいは、導かれる判断が循環をなしてしまい、結局どの事態をもたらすべきかについて答えを出せない――場合が発生しうることを示唆する。
アローの議論は専門的であるので、本論ではごく簡略化した例で要点を示すにとどめ、詳しい解説は他の研究書に譲る。なお、アロー自身は一般可能性定理を、社会的決定が独裁的な一個人の恣意によって左右されてしまう(我々の文脈で言えば、道徳判断が実質的にただ一人の選好だけを尊重するものとなる)場合が生じることに力点をおいて述べているが、私はむしろ、そうした社会的決定(道徳的決定)が循環をなしてしまい答えが出せない場合が生じることを強調する点で、アローとは論じ方が異なることをお断りしておく(付言すれば、選好を強度に応じて重んじる限り、功利主義はただ一人の極度に強い選好を他の全員の相反する選好より尊重することもあるような理論である。この可能性はしばしば功利主義の難点だと言われるが、私は全然そう思わない。虐められている一人の生徒の強い選好を他の全員の軽微な選好に反して尊重することに、何の不思議があるだろうか)。それでも、以下の議論が確かにアローの議論にヒントを得たものであることは間違いがない。
また、次のことも注意しておかねばならない。正確には、私がなしうる一つの行為は、普通、幾つかの事態をそれぞれある確率でもたらすと期待されるようなものであるだろう。それゆえ厳密には、私は、人々の選好を勘案して様々な事態の道徳的な望ましさを順位づけたのち、行為の各選択肢がどの事態とどの事態をどれほどの確率でもたらすと期待されるかを考えあわせて、なすべき行為を選択しなければならない。しかし、議論を簡略にするため、以下では一つの行為が一つの事態をもたらすと予想されているものとして論じることにする。
さて、次のような例を考える。私は21人の関係者を含む状況に関し、それぞれX、Y、Zという事態をもたらす三つの行為のいずれをなすべきかを考えている。このとき私は、21人全員の選好を考慮したといえるような道徳判断を下そうと思っている。しかし、私には他人の選好の強さは分からず、ただ三つの事態に関する各人の選好順序が分かるのみだとする。(2)そこで、私は、多数決と推移律を用いて、自分が道徳的に選ぶべき最善の選択肢を決めることにする。すなわち、私は二つの事態のうちより多くの人々に選好される方を、道徳的に望ましいとみなすべきである(この指令的判断を道徳的選好と呼ぶ)。また、ZよりYのほうが道徳的に望ましく、YよりXのほうが道徳的に望ましいなら、私はZよりXのほうが道徳的に望ましいと判断するべきである。さらに、この場合には私はZやYではなくXを最も望ましいとみなし、これをもたらす行為をなすべきであろう(もちろん、Xが最も望ましいという判断は、ただXの順位が一位であることを意味するのみであり、どのくらい望ましいかという判断は含んでいない)。これらは、選好強度を考えずに道徳判断を導く道具立てとして、ごく自然な推論に思える。
ところが、この問題状況で、1人がX>Y>Z、10人がZ>X>Y、10人がY>Z>Xの順に選好しているとしよう(X>Yは、XのほうがYより選好されていることを表す。なお、これにXとYの間で中立だという判断を含めるとX≧Yと表せるが、ここでは省略する)。このとき、(1)過半数(最初の1人と次の10人)がX>Y、また過半数(最初の1人と最後の10人)がY>Zのように選好しているので、それらに対応する私の道徳的選好が形成される。また、ここから推移律よりX>Zという道徳的選好も得られ、私はYやZではなくXをもたらすべきだという道徳判断を下すことになる。しかし、このX>Zという道徳的選好は1人を除く全員の選好に反する。20人がZ>Xという選好を示していたのだから、私はXよりZを望ましいと判断しなければならないはずなのである。さらに、(2)この20人のZ>Xという選好と、過半数がX>Yとしていたこととを考えあわせるならば、推移律により私はXやYではなくZをもたらすべきだという道徳判断を導くこともできる。しかしまた、(3)20人のZ>Xという選好と過半数のY>Zという選好を考えあわせれば、私はXやZではなくYをもたらすべきだという道徳判断を下すことになる。こうして、同様に多数決と推移律を使いながら、この状況について下される道徳判断は考察の手順によって変わり、一意的に決まらない。各々の事態をもたらす行為が相互排他的(一つの事態をもたらす行為を遂行するとき、他の事態をもたらすことはできない)であるならば、いま導かれた道徳判断は互いに矛盾する。もしくは、私が(1)でXを望ましいと判断した後に、20人のZ>Xという選好を考慮して「Zがより望ましい」と判断し直すなら、私はさらに過半数のY>Zという選好を考慮してYがより望ましいと判断しなければならず、さらに過半数のX>Yを考えてXがより望ましいと判断しなければならない(以下繰り返し)……という循環に陥り、結局何をなすべきかに答えを出すことができないのである。こうした事態は、今の例における10人をn人で表し、全部で(2n+1)人が関与する任意の状況において発生しうる。
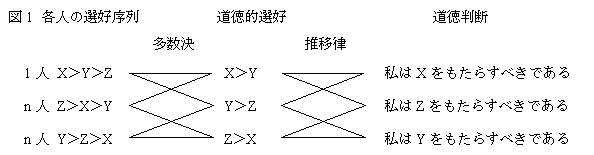
なぜ、このような逆説的事態が生じるのか。一つの大きな理由は、個々人の選好の強さ(ある選択肢を別の選択肢よりどのくらい強く望むか)を示すことができない点にあることが知られている。(3)特にこの例においては、選好強度ばかりか、選好順位の開きが全く考慮されていない。上図において、二つの事態にかんする道徳的選好X>Yを形成するにあたり、上二段のn+1人のX>Yという選好(順位の開きはいずれも一位差)と最下段のn人のY>Xという選好(Yは一位でXは三位という開きがある)とが全く同列に扱われている。このような選好の扱いをしたために、道徳的選好の循環が生じるのである。
順位評点法
しかし、以上の考察だけでは、選好強度の測定・個人間比較を拒否する人々から次のような意見が出るかもしれない。すなわち、選好順位の開きを考慮に入れるため、順位に応じて得点を付与し、それを集計する方式を採用しようというのである。このやり方は順位評点法と呼ばれる。例えば最上位に最も高い得点を与え、最下位に移行するに従って低い得点をつけ、最も合計点の高い選択肢を採用するような道徳判断を下せばよい。これは選好順序に応じて決まった得点を一律に配当するだけで、各個人の選好体系におけるその強度は考えていない。したがって、これは功利主義的な方法とは異なる。功利主義では各人が各順位につける値は各人にとってのその望ましさの程度で決められるので、異なる人々が各順位に同じ数値を与えるとは限らないのである。
さて、いま述べたような順位評点法においては、先の例のように結果が循環する恐れはない。しかし、このやり方でもやはり、我々にとって非常に奇妙に思えるような事態が生じる。その一つ(他にも考えられる)は、最終的には決して選ばれることのない選択肢が考慮に加えられるか加えられないかというだけで、下される道徳判断が異なるという事態である。
例えば、X, Y, Zという三つの事態に関する21人の選好順位が実際に次のようになっているとする。そして私は、この21人が関与する状況において、私がもたらしうる事態の選択肢の中から道徳的に最も望ましいものを選ぼうとしている。
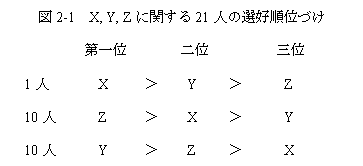
さて、私がもたらしうる事態がX, Y, Zの三通りあるとき、私は順位評点法を採用して、図2-1の第一位に3点、二位に2点、三位に1点をつけて集計する。すると、Xの合計点は33、Yは42、Zは51となり、私は「Zをもたらすべきだ」という循環のない道徳判断を下すことができる。一般化して、一位に数値a、二位にb、三位にc (a>b>c)をあてても同じ結果が得られる。
ところが、ここで、人々の実際の選好体系には変化がないが、私にはXを実現するのが不可能だったとしよう。私がもたらしうる事態はYとZだけである。このとき、私はYとZについての人々の選好だけを考慮することになるだろう。そこで、人々の選好体系は図2-1から変わらないとして、図2-1をYとZについての選好順位だけを表すように書き直すと次のようになる。
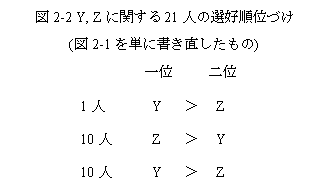
このとき、私がやはり順位評点法を採用し、第一位に2点、二位に1点をつけて集計するなら、今度は「私はYをもたらす行為をなすべきだ」という道徳判断が導かれる。 一般化して、一位に数値d、二位にe (d>e)をあてても同じ結果が得られる。
いま述べた二つの場合を我々はどのように受けとめるだろうか。Xは、図2-1の結論においても図2-2の結論においても結局は選ばれない選択肢である。このように最終的選択に関連のないXが可能か否かによって、「Zをもたらすべきだ」という判断から「Yをもたらすべきだ」という判断へと結論が変わるのは奇妙なことであろう。具体例をみれば、この奇妙さはいっそう明らかである。医師である私が、肝臓提供者から患者A, B, Cの誰に肝臓を移植すべきか迷っているとする。近くの病院にいる身寄りのないA(1人)は、肝臓が誰に移植されるかに関してA>B>Cという選好順位を形成している(Aが第一位なのは自分が助かりたい為であり、B>Cであるのは、Bのほうが私と提供者のいる病院に近いためである)。少し遠くの病院にいるBとその近親者(計10人)はB>A>Cである(A>Cであるのは同じくAのほうが近いためである)。さらに遠くの病院にいるCとその近親者(計10人)はC>B>Aである(B>Aであるのは、どちらかといえば彼らの近くに住むBとその近親者のほうに親しみをもつためである)。これらの21人はこの地域の肝臓病患者の会のメンバーであるので、彼らの選好はこの地域で肝臓移植がおこなわれる全ての場合に考慮されてしかるべきである。このとき、上の議論によれば、(適合性の都合で)Aに移植可能である場合にはBに移植すべきであり、Aに移植不可能である場合にはCに移植すべきだということになるのである。この結論は非常に奇妙であろう。Aはいずれの場合も結局は移植を受けないのに、なぜ彼の存在によってBに移植すべきかCに移植すべきかの判断が左右されねばならないのだろうか。ところで、この奇妙な事態が生じる一つの理由も、選好の強さが全く無視されていることにある。中段の10人のZ>Yという大小関係が、図2-1から図2-2に移行する際に圧縮されていることに我々は気づくべきである。
もちろん、奇妙な事態が生じるというだけでは、我々が以上のやり方を採用すべきでないと主張する十分な理由にはならない。また多数決と推移律による方法でも、循環や矛盾が生じるのは一部の場合に限られるので、このようなパラドックスが時に生じうるというだけならこの方法を一般に採用して構わないという人もいるかもしれない。しかし、より整合的に道徳判断を導く方法があるなら、つまり循環が生じたり関連のない選択肢に左右されたりしない方法が他にあるならば、そちらを採用したいと我々は思うのではないだろうか。
しかしまた、以上の議論から直ちに、「より整合的な方法」が選好強度をはかる方法でなければならないとの結論が出てくるわけではない。選好強度を考慮しないで、かつ逆説的事態を生じない別の方法を組み立てることはできるかもしれない。アロー以後の社会的決定理論でも幾つかの方法が探究されているようである。しかし今のところ、選好強度を考慮しないまま、整合的で、かつ恣意的でないような(しかも、妥当な道徳理論たりうるような)選好集計方法を構築するのは難しいように見える。そのような方法でうまく構築されたものがあれば検討に値するが、功利主義をテーマとする本論ではこれ以上は論じない。私はただ次のことを指摘しておく。もし人々の選好強度が何らかの手法によって共通な尺度で測定できるなら、各選択肢についての個々人の選好強度を加算することによって最も望ましい選択肢を確定できるだろう。基数的効用(選好強度に応じて数値化された、選好対象の望ましさ)を我々が扱えるとした場合、個人的効用関数から整合的な社会的厚生関数を構成できると論じているのはハルサーニである(Harsanyi
1976, 1977)。
3. 個人間比較の構造:ハルサーニの考察
しかし、我々が選好強度を考慮するとすれば、当然問題になるのは、ではどうやって他人の選好の強さを知り、彼の選好体系を選好強度を含めて表現できるのかということである。
今日では、ある時点の一個人の選好体系については、フォン・ノイマンとモルゲンシュテルンが提案したような方法を使って、様々な選好対象を選好強度に応じて一つのスケール(物差し)に表示することが可能だと主張されるようになった。この方法によれば、様々な対象のうち個人が最も選好するもの(最上位)と最も選好しないもの(最下位)が確かめられたならば、確率を配分した賭けを利用して、その他の選好対象が両者の中間のどの辺りに位置するか、つまり最下位よりどのくらい上位にあり、最上位よりもどのくらい下位にあるかを決めることができる。これらの対象は最下位からから最上位までの一つのスケールに表すことができ、各選好対象のスケール上の位置は数値化して基数的効用として表すことができる。もっとも、この方法では、二つの対象の一方をより望む、あるいは二つの間で中立であるといった選好関係が推移的で完全な仕方で表せること、また確率を配分した賭への選好を人がもつことができ、その選好の中には中立的選好も含まれること、など計四つの仮定がおかれるが、本論では深く論じない。このノイマン-モルゲンシュテルン方式の基数効用の測定と、個人的選好スケールの作り方については、ライカー 1991 p. 114 ff., Harsanyi 1976, Jeffrey 1965 p. 44 ff.などを参照されたい。
さて、いま述べたやり方によってある時点のある人の選好スケールを得ることはできるかもしれない。しかし、私がこれを、現在の私や別の時点の別の人の選好スケールと直ちに比較できるわけではない。上記の方式によって得られる一時点の個人の選好スケールとは、その時点の彼の様々な選好対象が最上位と最下位との間にどのような間隔で並んでいるかを示すものでしかない。そして、ある人の最下位より最上位を好むという選好の強さは、別の人の最下位より最上位を好むという選好の強さとは異なるかもしれない。したがって、私が様々な時点の複数の人々の選好スケールを単に集めてみるだけでは、いわば目盛りの幅が異なる様々な物差しを取り集めたことにしかならないのである。これらの物差しの間で私が効用の個人間比較をおこなうためには、私は目盛りの幅と効用0となるような原点とを揃えなければならない。原点については、現状維持という事態や選好も嫌悪もしないような事態が位置する点を選ぶなどして、人々の間で共通な仕方で揃えることはできよう。問題は目盛り合わせである。
選好強度の個人間比較にはこの目盛り合わせという作業が必要であることを指摘し、この論点を掘り下げているのは、先ほど言及したハルサーニである。道徳判断を下そうとしており、そのために人々の選好をその強さを含めて比較しようとしている人は、現時点の自分を含めた各個人の各時点の選好スケールを、適切な共通の単位で表されたスケールに変換しなければならない。このとき、彼がしなければならないことは、各々のスケールを共通単位で表されたスケールへと変換するための転換比(conversion ratio)を設定することである。ハルサーニにならって個人iの選好スケールを個人的効用関数Uiとして表すならば、次のように述べることもできる。個人iが自分を含むn人の関与する状況について、いかなる事態をもたらすべきかについて道徳判断を下そうとしており、そのために様々な事態の各人にとっての効用を比較考量しようとしているならば、彼はこのn人の個人的効用関数U1,..., Ui,..., Unを共通の効用単位へと変換する転換比q1,..., qi,..., qnを設定しなければならない。そうして、U1*=q1U1,..., Ui*=qiUi,..., Un*=qnUn となるU1*,..., Ui*,..., Un*を比較することによって、初めて適切な個人間比較が可能となるのである。異なる時点の選好スケールについても同様のことをしなければならない(次の図を参照)。
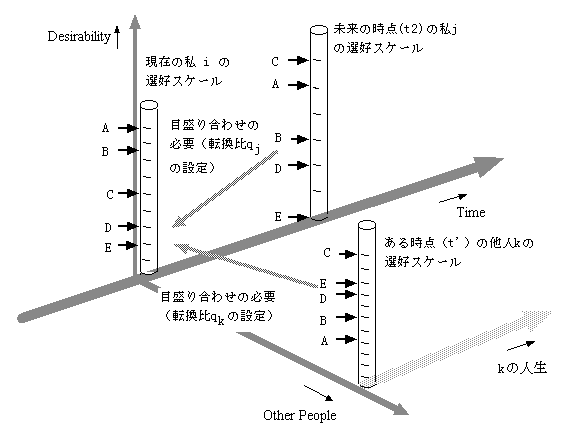
この図では、道徳判断によって影響を受ける関係者として、現在の私、未来の時点の私、そしてある時点の他者がいると想定している。道徳判断を下そうとしている私は、これらの選好スケールを現在の自分の選好スケールとも突き合わせて比較しなければならない。それぞれの選好スケールは、各時点の各人における、AからEまでの対象の彼の中での相対的な望ましさを示してはいるが、三つのスケールに共通の単位(共通の目盛り)で表されたものではない。例えば、現在の私iのスケールは、現在の私においてCをEより望む強さはDをEより望む強さ(これがこのスケールの一目盛りをなしている。これをunit(i)と呼ぼう)の三倍であることを示している。未来の私jのスケールは、jにおいてCをDより望む強さがBをDより望む強さ(unit(j))の四倍であることを示している。他人kのスケールは、彼においてCをDより望む強さがEをDより望む強さ(unit(k))の三倍であることを示している。しかし、iにおけるunit(i)と、jにおけるunit(j)と、kにおけるunit(k)が同じ強さだとはいえない。私が三者の選好を比較するためには、これらのスケールを、適切な転換比を用いて、共通単位で表されたスケールへと変換しなければならないのである。
さて、この転換比を設定するのは、道徳判断を下すために選好の個人間比較を試みている当人である。では、彼はどうやって各人の効用単位を共通の単位へと揃える「適切な」転換比を設定するのだろうか。彼は結局、この段階で、各スケールにおける選好(そうである必要はないが、例えば各スケールの一目盛りをなすような選好)の強さを個人間で比較しなければならない。前頁の図で言えば、彼はunit(i)とunit(j)とunit(k)を、個人間あるいは異なる時点の間で比較しなければならないのである。では、どうやってそれを行うことができるのだろうか。
これに関して提案されている工夫が、想像上の立場交換という思考実験によって、自分の心のうちに他人の選好を含めた主観的態度を再現し、「彼と同じ主観的態度をもって彼と同じ立場におかれること」と「自分の主観的態度をもって自分の立場におかれること」の間での自分自身の選好を形成してみる、というものである。この種の選好はハルサーニが「拡張された選好」と呼ぶものである。また、上述のように選好の個人間比較を否定した場合のパラドックスを論じたアローも、その後の1963年の覚え書きの中で、「拡張された共感」という名で、同様の手法が個人間比較の基礎となりうる可能性を述べている。「拡張された」というのは、私の通常の選好が現実に起こりうる事態の間のものであるのに対して、この新しく形成される選好は、少なくとも一方の選択肢が「彼と同じ主観的態度をもって彼と同じ立場におかれる」という、私の想像を拡張することによって想定された仮想的事態だからである。
この拡張された選好は、私が、他者の選好と自分の選好とを私の内部で間接的に比較するのに役立つ。(4)他人がおかれる事態と彼の主観的状態とを、事実に照らしてできる限り正確に心のうちに再現し、「事態yにおいて彼であるよりも、事態xにおいて私自身である方が(私の判断では)よい」という拡張型選好を形成することによって、私は間接的に、<事態yに対する彼の選好>と<事態xに対する私の(拡張型でない)選好>とを比較するのである。これは言うまでもなく、ヘアが、想像上の立場交換と他者の選好の再現によって、選好の個人間比較を同一個人の内部での比較に移し替える、と論じるときに試みているものにほかならない。
この拡張された選好を用いて、ある事態に対する他人(または別の時点の人)の選好の強さと別の事態に対する私の選好の強さとを間接的に私の心の中で比較することで、私は少なくとも私にとって適切に思えるような転換比を設定できるだろう。それによって、私は少なくとも自分の中では十分に整合的な仕方で自他の(変換された)選好強度を比較することができる。
4. 個人間比較の難点は何処にあるか
しかし、我々が注意しなければならないのは、拡張された選好を形成するのはあくまで道徳判断を下そうとしている当人であり、転換比を設定するのもこの個人だということである。ハルサーニも気づいているように、異なる個人の拡張型選好が一致するとは限らない。同様に、異なる個人が同じ転換比q1,…, qi,…, qnを選ぶとは限らない。たとえ私が上記のような拡張型選好を形成したとしても、他人である彼の方は、事態xにおいて私であるよりも事態yにおいて彼自身である方が(彼の判断では)よい、という正反対の拡張型選好を形成しているかもしれない。そして、どちらの拡張型選好が<事態xにおける私の選好>と<事態yにおける彼の選好>の強さの違いを「正しく」反映しているのか、またどちらの転換比が「真の」転換比であるのかは、誰にもわからない。
選好再現、拡張型選好の形成、および転換比の設定という手法は、確かに意義のあるものである。これらの手法は、道徳判断を下そうとしている人が、諸個人の選好強度や効用を、彼の心の中で整合的に比較することを可能にしてくれる。しかし、これらの手法は、彼が行う個人間比較が、同じように道徳判断を下そうとしている他の人々が行う個人間比較と一致することまでは保証しない。各人が形成する拡張型選好や採用する転換比が異なるならば、各人が心の中で行う選好スケールの変換に違いが生じるだろう。このことは、たとえ人々が、諸個人の選好を強さに応じて重んじ、それらを最大限に充足させる行為を選ぶ道徳判断を下すことに同意したとしても、各人が同じ状況に下す道徳判断が異なる可能性があること-------つまり、道徳的合意が得られない可能性があること-------を示している。選好強度の個人間比較にまつわる最大の問題は、この点にあると言えよう。我々は、深刻な道徳問題が生じているときには、自分の中で整合的な道徳判断を下せることだけでなく、人々が合意してくれるような道徳判断を下すことを望むだろう。合意を得られない可能性が残ることは、我々にとって非常に不安である。
ハルサーニは、人間の選好は基本的な心理学的法則に支配されているという仮説をたてることにより、我々が慎重に行う選好の個人間比較はある程度客観的な妥当性をもちうるだろう、と論じている。人々の選好は一見すると非常に異なる選好をもつが、そうした選好の違いは、様々な要因(その人の生理的特徴や過去の生活史、社会的立場、文化的環境など)が人間の選好に及ぼす影響についての一般的な心理法則によって理解できるかもしれない。もしこのことが正しいなら、ある他人の選好の強さについての私の判断は、人間の基本的な心理的法則の知識を私が得るにつれて、また彼の立場や彼の生理的特徴や環境についての知識が増すにつれて、正確に、そして客観的にみて妥当な(つまり、同じ知識を得た人々が同意するような)ものになっていくと想定してよいのではないか、というのである。人々の幸福を選好強度によって比較しようとするブラントも、またヘアも、この点に関しては同様の意見である。実際、選好強度の個人間比較を行うことを正当化するにあたっては、このような想定をおいて議論することしか我々にはできないに違いない。しかし、この「人間の基本的な心理構造は同じである」という主張は仮説にすぎない。
個人間比較の真の困難は、上に述べた二つの部分に存する。すなわち、(1)個人間比較の集計結果が異なる人々の間で一致しない可能性があること、そして、(2)その一致を期待するべく人間の心理に関する一般的説明を用いるとしても、その説明はあくまで仮説にすぎないということ、である。
これら二点の困難をより詳しく述べる。注意しておきたいが、個人間比較の困難は、選好強度の個人間比較が、比較している主体の内的整合性を保つような仕方ではなしえない、ということではない。個人が自分の心の中で整合的な仕方で個人間比較をおこない、一つの解答を導くことは、全く可能なのである。問題は、その解答が人々の間で違いうるということ、そしてそのように解答が異なった場合、そのうちのどれが妥当な解答かを判定するのは不可能だということである。我々が見たように、人ごとに転換比の設定が異なれば、同じ状況に関して人々の選好強度の個人間比較をしたとしても、その集計結果が人によって違ってくる可能性がある。そして、そのような集計結果のうちどれが妥当なものであるかを、我々が判定するのは無理なのである。
これに対し、例えばハルサーニのような心理学的仮説をたて、それによって人々の間での転換比の一致を期待することはできる。しかし、この議論の路線をとるとすれば、この心理学的仮説の妥当性を我々は示さなければならない。そしておそらく、この仮説を信じることはできても、これを立証することはまず無理である。この点に、やはり選好強度の個人間比較の難点がある。
選好強度の個人間比較の問題は、以上の二点にある。それでも私は、この種の比較の難点を指摘しながら功利主義を支持し続けたシジウィックと同じように、自他の選好強度を比較し続けるであろう。その比較は間違っているかもしれないが、私が何か一つの道徳的決断を下そうとする限り、私はそうした比較を行なおうとするだろう。その場合に私が覚悟するべきは、そのような選好の個人間比較が私にとって整合的な仕方でできないということではなく、その私の判断が同じ事態を考慮する他者の判断と食い違う可能性が常にあるということ、そして、私が前提している「彼の現在の性格と、一般的な心理的法則と、彼の背景的要因の全てがわかれば、彼がもつであろう選好の強さは推定しうる」という考えはあくまで仮定にすぎないということである。私の経験では、この仮定に深刻な疑いをなげかけるような事実はこれまで生じておらず、むしろ人間の心理には共通の一般的法則がありそうだということを示す事実の方が多いように思われるので、私はこの仮定を放棄せず、選好強度の個人間比較を続けている。そして、それと同じ理由から、他の功利主義者たちも選好強度の個人間比較を提唱し続けるのである。(5)
[付記]本稿は学位論文の一部(第11章1、2節)に加筆・修正を施し、単独の論文としたものである。学位論文の中では、同じテーマがヘンリー・シジウィックの倫理学説との関連で論じられている。拙稿「シジウィックと現代功利主義」を参照されたい。
文献
Arrow, K. J., Social Choice and Individual Values, John Wiley and Yale U. P., 1951.2nd edition, 1963. (邦訳『社会的選択と個人的評価』長名寛明訳、日本経済新聞社、1977)
Brandt, Richard B., A Theory of the Good and the Right, Oxford: Clarendon Press, 1979.
Glover, Jonathan (ed.), Utilitarianism and Its Critics, New York: Macmillan, 1990.
Hare, R. M., Moral Thinking, Oxford: Clarendon Press, 1981. (邦訳『道徳的に考えること』内井惣七・山内友三郎監訳、勁草書房、1994)
Harsanyi, John C., "Cardinal Welfare, Individualistic Ethics, and Interpersonal Comparisons of Utility", Journal of Political Economy 63(1955) 309-21. Reprinted in Harsanyi 1976.
-------, Essays on Ethics, Social Behaviour, and Scientific Explanation, Dordrecht: Reidel, 1976, Reprinted in 1980.
-------, Rational Behaviour and Bargaining Equilibrium in Games and Social Sciences, Cambridge U.P., 1977.
Jeffrey, Richard C., The Logic of Decision, U. of Chicago Press, 2nd ed., 1983 (1st ed., 1965).
Mill, John Stuart, Utilitarianism, 1861. London, 1863.
Rawls, John, A Theory of Justice, Cambridge, Mass: Harvard U. P.,1971. 邦訳(『正義論』矢島鈞次監訳、紀伊國屋書店、1979。)
Seanor, D. and Fotion, N. (ed.), Hare and Critics, Oxford U. P., 1988.
Sen, Amartya K., "Rational Fools: a Critique of the Behavioural Foundations of Economic Theory", Philosophy and Public Affairs 6 (1977b) 317-44. 邦訳(『合理的な愚か者』大庭健・川本隆史訳、勁草書房、1989)所収。
Sen, Amartya and Williams, Bernard (eds.), Utilitarianism and Beyond , Cambridge U. P., 1982.
Sidgwick, Henry, The Methods of Ethics, 1874. 7th edn. London: Macmillan, 1907, 1962. Cambridge: Hackett, 1981. (第五版の邦訳『倫理学説批判』中島力造校閲、山辺知春・太田秀穂訳、大日本図書、明治31。)
Smart, J. J. C. and Williams, B. A. O., Utilitarianism: For and Against, Cambridge: Cambridge U. P., 1973.
Uchii, S., "Moral Reasoning", Zinbun 13 (1974): 61-81.
-------, "Utility and Preferences", paper presented at the symposium
on J.S. Mill, October 25, 1998, Japan Association for the History of Economic
Thought. See also http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/~suchii/util%26pref.E.html,
1998.
(邦語版「功利と選好」、1998年経済学史学会、10月24日、共通論題「J.S.
ミルと現代」、http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/~suchii/util%26pref.html)
内井惣七「倫理学の方法」『人文研究』34、1982。
-------『自由の法則、利害の論理』ミネルヴァ書房、1988。
-------『進化論と倫理』世界思想社、1996。
奥野満里子「シジウィックの快楽説再考」関西哲学会編『アルケー』No. 6 (通巻33号、July.1998)、1998。
-------「シジウィックと現代功利主義」京都大学大学院文学研究科学位論文、1998。
神野慧一郎「倫理の理論における効用の概念」『哲学研究』第510号。
佐伯胖『「きめ方」の論理------社会的決定理論への招待』東京大学出版会、1980。
塩野谷祐一『価値理念の構造』東洋経済新報社、1984。
柴田弘文・柴田愛子『公共経済学』東洋経済新報社、1988。
鈴村興太郎『経済計画理論』筑摩書房、1982。
曽根泰教『現代の政治理論』放送大学教育振興会、1989。
ライカー、ウィリアム H.『民主的決定の政治学』森脇俊雅訳、芦書房、1991。
(敬称略)
(おくの まりこ 日本学術振興会特別研究員)
(2)
正確に言えば、このとき各人の選好は常にこの選好順位にしたがう整合的なものだと想定されている。つまり、ある人がX、Y、Zの順に選好するというなら、彼は常にXをYより選好し、YをZより選好し、XをZより選好する。これは、各個人もまた推移律を満たすということである。人の選好は必ずしもそうした整合的な順序をなさないという主張もあるが、全く無秩序であったとしたならそもそも人々の選好を考慮することはほとんど無理であり、無駄であるだろう。少なくとも理想的には整合的なものと想定したほうが生産的である。道徳判断の整合性についても同様である。とくに、以下に述べるように、道徳判断を下そうとする私の選好(道徳的選好)が推移律を満たさない場合、道徳判断を下そうとする営みがそもそも無意味になる。
(3)
例えば、柴田 1998, pp. 266-7、佐伯 1980, p. 121. ただし、佐伯氏は別の研究者ング(Ng)の指摘を紹介する形で述べており、佐伯氏自身は選好強度を考慮に入れることに批判的である。
(4)
二人の他者の選好や、同一の他者の二つの選好を私が比較するのにも役立つ。しかしこの仮想的事態についての想像はより難しくなるので、私はノイマン-モルゲンシュテルン法によって得られる他人の選好スケールと照合して想像の正しさを点検するだろう。詳しくはハルサーニ自身の議論を参照されたい。
(5)
もちろん、我々はここで最後の注意をしておかなければならない。我々が人々の選好強度を共通の尺度で測るということを認めたからといって、我々が直ちに功利主義者になるわけではない。選好強度を測るからといって、人々の選好をその強さに比例して重んじること、また各人の選好強度の総和最大化をもたらす選択肢を選ぶこと、を認めるのでなければ功利主義にはならないのである。ロールズのように、人々の選好の強さを実際には考慮していながら(誰が不遇であり、最も助けを必要としているかを考えることによって)、単純に強さに応じて重んじるのではなく、最も恵まれない人の選好に多めの重みをおくという立場もある。また効用の集計方法に関しては、ロールズのように格差原理を採用する立場もあるし、人々の効用の和ではなく積によって道徳的評価をするという効用乗算原理を採用する意見もあるのである(cf.
ライカー 1991,p. 118)。基数効用の総和原理と、格差原理や効用乗算原理といった代替案とのどちらが信頼できる効用の集計方法であるかについては、今の私には総和原理が明快であり恣意的でないように見える、という以上に何とも言えない。どの集計方法が望ましいかは、これらの原理が現実の問題に適用された場合にどのような結論を導くかを確かめることによって、徐々に検討していくのがふさわしいのではないかと思う。この検討は功利主義理論にとってのもう一つの課題である。